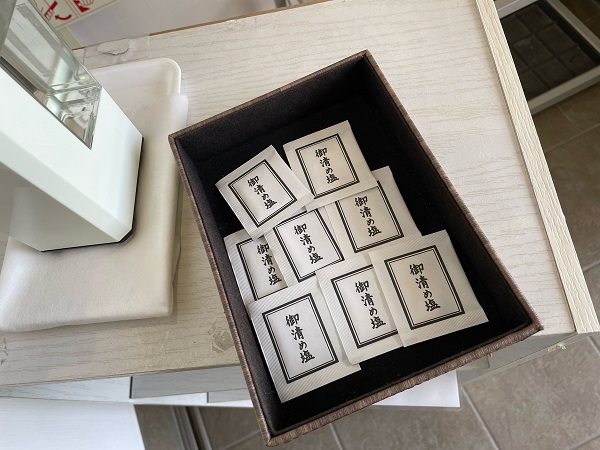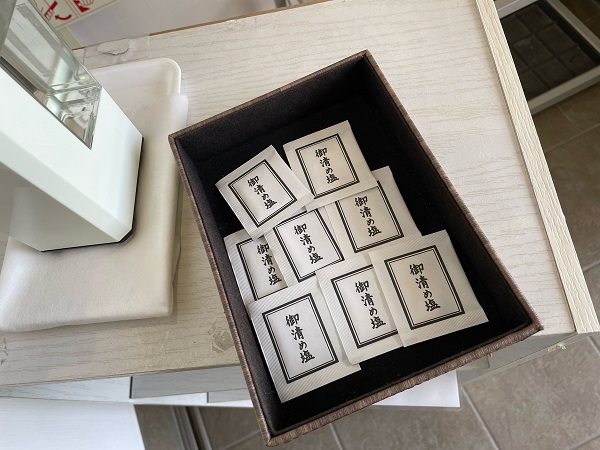みなさん、こんにちは。
本日も絆ブログをご覧いただきましたありがとうございます。
突然ですが、本日4月13日がなんの日かご存知でしょうか。
言われているものはいくつかありますがその中で「新型インフルエンザ対策の日」というものがあります。

2009年、4月13日にメキシコで最初の新型インフルエンザ患者が確認され後に亡くなってしまいました。
その後、世界的に広がり多くの感染者や患者を発生させるパンデミック(世界的流行)と認定されました。
翌年、新型インフルエンザへの備えを怠らないようにとの思いをこめ一般社会団法人・日本人記念日協会により認定・登録されました。
ちなみに通常のインフルエンザと新型インフルエンザの違いは何なのかというと、通常のインフルエンザは日本の冬季に毎年流行する季節性インフルエンザのことを指し、新型インフルエンザはこれまでに人が感染したことのない新しいタイプのインフルエンザです。
新型インフルエンザは特定の季節が決まっておらず冬以外も通年を通して流行する可能性があるのです。
コロナウイルスが落ち着き、季節製のインフルエンザ・風邪等も落ち着いた今一度感染対策に勤しんでいただけたらと思います。
手洗い・うがい、咳エチケット、マスクの着用などで予防ができます。
自分だけでなく、自分の大切な人を守るためにどの季節も予防をしていきましょう。
平安会館・文十鳳凰殿
馬場
平安会館・文十鳳凰殿 公式Instagram・Facebook・Twitterでも葬儀の様子や豆知識などをご紹介しております。
ぜひご覧ください!
◇平安会館
◇文十鳳凰殿