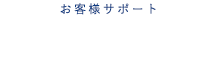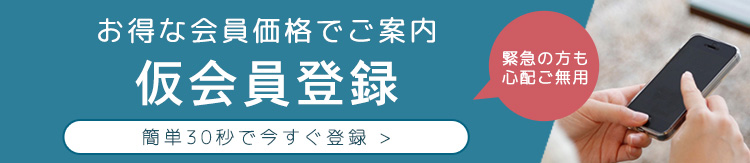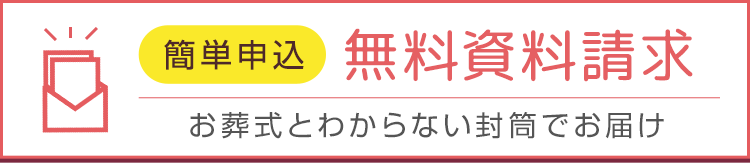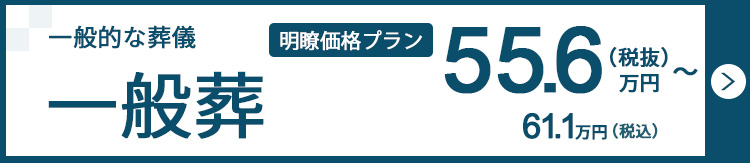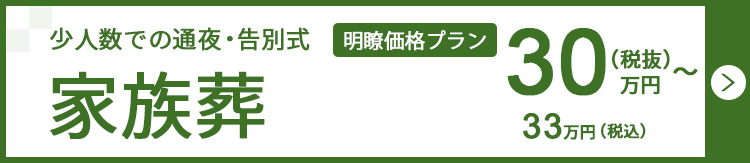先月、秋のお彼岸参りが近いころ、あるお寺様より「六波羅蜜」というお考えについて教えていただきました。
波羅蜜とは悟りの世界である彼岸に至ることを言います。
大乗仏教においてお釈迦様が実践された六つの修行を実践することで煩悩を消し去り、心の平安を得ることが出来るとされているのが「六波羅蜜」です。
本日はその六つをご紹介させていただきます。
- 「檀波羅蜜 又は 布施」
貪欲な気持ちを抑えて、見返りを求めず物や心を分け与える施しこそが最上である
- 「尸羅波羅蜜 又は 持戒」
戒めとは非を防いで悪を退けること。自分自身を律し正しい生活習慣を身につけること。
- 「闡堤波羅蜜 又は 忍辱」
どのような辱めを受けても決して怒らぬこと。耐え忍び修行や学びと捉えること。
- 「毘梨那波羅蜜 又は 精進」
不断の努力。限りある人生をひと時も無駄にすることなく日々誠心誠意を尽くすこと。
- 「禅波羅蜜 又は 禅定」
心を落ち着かせ何事にも動じない精神を保つ、第三者の立場で自分自身を見つめること。
- 「般若波羅蜜 又は 智慧」
上記五つの実行によってすべての事物や道理を見抜く深い知恵をもつこと。

はじめ「六波羅蜜」という言葉を聞いた際は、鎌倉幕府が設置した「六波羅探題」が思い浮かんだのですが、あながち遠からずの面もあるようです。
京都には「六波羅蜜」に因んで名付けられた「六波羅蜜寺」というお寺がございます。
その近くの地名はのちに六波羅と言われるようになり、1221年の承久の乱後に鎌倉幕府が朝廷の監視と西国における武士の紛争や御家人間の裁判、治安維持を目的として「六波羅探題」を設置したようです。
仏教の教えに触れたつもりが、思わぬ形で歴史との繋がりも感じさせられました。
ご紹介させていただいた「六波羅蜜」。
しがらみや迷い、喜びも悲しみも溢れる長い人生を迷いなく穏やかに生き抜くための一つの指針となる教えでした。
平安会館 文十鳳凰殿
河本
平安会館・文十鳳凰殿 公式Instagram・Facebook・Twitterでも葬儀の様子や豆知識などをご紹介しております。
ぜひご覧ください!
◇平安会館
◇文十鳳凰殿